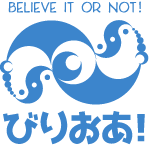“春”と聞いて連想するものといえば?
きっと多くの人が“桜”と答えるでしょう。
桜は日本人が愛してきた花です。
100円硬貨にも桜が刻印されていますし、
志望校への合格を電報で伝える文言は、「サクラサク」でした。
春先に咲き乱れ、そよ風に吹かれ散っていく桜。
桜を眺めることを、毎年の楽しみにしている人も少なくないでしょう。
満開の桜並木には、胸を打つ感動を覚えることがあります。
お花見を恒例行事にしている人もいるかもしれませんね。
そんな桜を眺めていると、頭をよぎるこんな噂。
「桜の木の下には死体が埋まっている」
そう、桜は元来不吉なものだったのです。
梶井基次郎『櫻の樹の下には』

「桜の木の下には死体が埋まっている」という噂の元になっているのが、
明治時代の小説家・梶井基次郎の短編小説『櫻の樹の下には』の冒頭の文章です。
「桜の樹の下には屍体が埋まっている!」
『櫻の樹の下には』は、この衝撃的な一文から始まる、4ページほどの短い短編小説です。
その内容は、
桜があれほど美しいのには何か理由がある、と桜の美しさに不安を感じる主人公。
美しさと対局にある死体という醜いものが樹の下に埋まっていると想像することで、不安から解放される、というもの。
小学生の時に、こんな理科の実験をしませんでしたか?
赤い色をつけた水に白い花をつけておくと、
花は水を吸い上げ、やがて白い花びらは赤く染まっていく。
そして桜の花びらは淡いピンク色。
しかし、中には鮮やかな赤い花を咲かせる桜の木がある。
その桜の木の下には死体が埋まっていて、死体の血を吸って桜の花が赤く染まったのだ。
この噂は、梶井基次郎の小説の一文に尾ひれがつき、広まっていったものと推測されます。
しかし話はここで終わらない。
他のサイトでは概ね、「梶井基次郎の小説が元ネタ!」で考察が終わってしまうのですが、
私はさらに元になる話やモチーフがあるのではないかと考えました。
そう思って調べてみると、
元来、桜は不吉なものだとされていたことがわかったのです。
江戸時代まで桜は不吉なものだった

意外なことに、江戸時代頃までは桜は不吉なもの、縁起の悪いものだとされていました。
その理由は、桜には「散る」というイメージが強かったため。
桜の花はパッと咲いてパッと散るもの。
それを「人の死」や「物事の失敗」と関連付けて、桜は縁起が悪いものだと考えていたようです。
椿も桜と同じように縁起の悪い花だと考えられていました。
椿の花は根元からボトリと落ちるので、その様子がまるで首を斬られたみたいだって。
だから武士の家の庭には、椿は絶対に植えなかったのです。
また、桜の花びらは、散った後すぐに色褪せることから、「心変わり」を意味していると考えられていました。
そのため、桜の季節の結婚は縁起が悪いと避けられていたのです。
その他にも、墓地や戦場跡地などに桜が多く生えていることから、
桜は人骨を吸って育つなどの言い伝えや、
桜の木の根元には鬼や霊が棲んでいるという伝承も存在します。
時代が下り、江戸時代中期ころから「桜はめでたいもの」という意味になったらしく、この頃よりお花見が庶民の楽しみになりました。
桜を庭に植えると縁起が悪い

庭に桜があれば、毎年お花見ができていいじゃないかと思えます。
しかし、「桜を庭に植えると家が栄えない」と言われており、
庭に桜を植えることは敬遠されることが多いようです。
その理由は、桜が育つのにあたり、たくさんの養分を吸い取る木であるため。
だから桜を植えてしまうと、庭に植えてある他の木の栄養まで吸い取ってしまい、枯れさせてしまうのです。
また、大きく枝葉を広げて成長するため、やがて家の日当たりが悪くなります。
「桜切るバカ、梅切らぬバカ」という言葉がありますが、
桜は枝を切ると枯れてしまいやすくなるため剪定ができません。
そのため、枝は伸び放題になって日照障害を起こし、木造住宅を早く傷めてしまうのです。
風水で「庭に母屋よりも高くなる木を植えるのは凶」と言われています。
その理由はここにあるのかもしれません。
桜は根が強く、縦横に大きく根を張る木でもあるので、
伸びた根が家の基礎を持ち上げたり、排水溝を破壊する危険性があります。
街路樹に桜を見ることがないのは、大きく伸びた根がアスファルトを抉ってしまうからです。
一方、堤防の護岸には適しているので、河川沿いの堤防に桜並木が多く見られるのはこれが理由です。
確かに桜の名所は川原横の道沿いとか、
広い敷地を持ってる公園やお寺ってイメージがある!
その他、大量の毛虫が発生したり、落ち葉の掃除が大変だったりと、
手入れが大変で庭木に向かないと言われています
「桜を庭に植えると縁起が悪い」とは、
庭木として手入れが大変であったり、
住んでいる家を傷めてしまうことがその由縁となっているのでしょう。
京都三条河原の桜並木

京都、鴨川沿いにある三条河原。
春になると鴨川沿いには美しい桜が咲き乱れます。
以前にこちらの記事でも触れましたが、三条河原はかつて処刑場でした。
例えば豊臣秀吉は、甥の秀次の親族を連れ出し、三条河原にて次々に首をはねています。
さらに秀吉は、三条河原で石川五右衛門を釜茹での刑に処しています。
新鮮組の近藤勇は東京・板橋で斬首された後に晒し首にされたのが三条河原でした。
元刑場など、不吉なイメージがついた土地は買い手もつかず、誰も利用しません。
そんな不吉なイメージを払拭するため、派手で鮮やかな花を咲かせる桜を川沿いに植えたのではないか、という噂があります。
関連記事 →「学校が建っている所は昔墓地だった」という噂話は本当か?
おわりに
椿の花も、散る時に首の根元からボトリと落ちることから、武士の「介錯」を連想させる不吉な花だと言われていました。しかし時代が下るにつれ、着物の意匠に使われたり、庭木としても人気がある木になっています。
時代の移り変わりとともに、イメージはどんどん変わっていくのでしょう。
夜の桜を眺めている時にふと感じる妖しさ。
それは「桜はめでたいもの」という”現代人の感覚”と、
「桜は不吉なもの」という”日本人古来の感覚”とが
合わさった不一致から生じる揺らぎなのかもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。