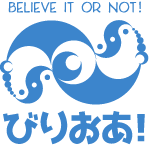大阪の大商業エリア、梅田。
若い人を中心に多くの人が行き交う繁華街の真ん中に、「歯」にまつわる神社があるのをご存じでしょうか。
小さな神社ですが、歯に関する様々なことにご利益があるという珍しさから、大阪では知られた神社の1つとなっています。
父が歯を悪くしたこともあり、歯の健康をお祈りするため大阪梅田の歯神社まで行ってきました。
なぜ歯にご利益のある神社となったのか?
歯神社の御利益の由来と合わせて、
歯神社までの行き方や、お守りや御朱印のいただき方を紹介させていただきます。
この記事の目次
歯神社へのアクセス

歯に関する様々なことにご利益があるという「歯神社」。
そんな歯神社は、大阪梅田にある商業施設「EST(エスト)」の裏手にあります。
つい見過ごしてしまいそうな、とても小さな神社です。
私が阪急電鉄の沿線に住んでいますので、阪急梅田駅からの行き方を紹介します。
まず阪急梅田駅の中央改札口から構外に出ます。
梅田駅の中央改札口は、2階と3階の2ヶ所ありますが、どちらから出ていただいても構いません。
下りのエスカレーターに乗り、1階を目指してください。
すると阪急三番街の南館1階に着きます。
そして左手側にある、「HEP FIVE」または「HEP NAVIO」へ通じる出入り口から館外へ出ます。
そうするとJRの高架下に「EST」という商業施設が目に入るはずです。

幅広の横断歩道を渡り、「EST」と赤い観覧車が有名な「HEP FIVE」の間の道を進み、


交差する道を左へ曲がると・・・
高架下をくぐった所で小さな赤い鳥居が見えてきます。

そこが歯神社です。
歯神社にあるのは小さなお社と「なで石」
歯神社の説明ついて何度も「小さな」と書いていますが、本当に小さな神社です。人がくぐれるくらいの鳥居とお社があるくらい。

その前には「なで石」という小さな丸石(御神体の巨石のかけら)があり、

このなで石を2~3度なでた手で歯の痛いところをさすれば痛みが和らぐと言われています。
「歯止め」が転じて「歯痛止め」の神様に
歯神社の主祭神は歯神大神さまで、親しみを込めて「歯神さん(はがみさん)」と呼ばれています。もともとは、この地にあった巨石に神が宿っているという信仰があり、地元の人々によって祀られたことが由来のようです。
歯神大神さまはウカノミタマノカミ様のことらしく、「歯の神様」として信仰を集める前はごくありふれた「お稲荷様」だったのでしょう。
御神紋が「抱き稲」となっているので間違いなさそうです。
関連記事 → お稲荷様は危険な怖い神様!?

お稲荷様は危険な怖い神様!?神社を参拝したらずっと信仰し続けないと祟るってホント?
「おいなりさん」の名前で親しまれている稲荷社は、日本で最も数が多い神社です。 その数は全国で2万社におよぶといいます。
それではなぜ「お稲荷様」が「歯の神様」となったのでしょうか。
歯神社の由緒についての説明書きによると、
数百年前ほど昔のこと。
近くを流れる淀川が氾濫し、梅田一帯が大洪水に見舞われた際に、
お社の御神体であった巨石が歯止めして梅田が水没するのを防いだ
という伝承があるようです。
このことから「歯止めの神様」と慕われるようになり、
やがて語呂が転じて「歯痛止めの神様」に変化したと考えられています。
また第二次世界大戦の時に大阪は大空襲に見舞われ、梅田一帯は火の海となりました。
しかしこの時も歯神社までは火が届かず、戦火を歯止めしたとも云われています。
歯神社は「歯痛止め」以外にも御利益がある!

歯痛に効く神様として、篤い信仰を集めている歯神社ですが、
「歯痛鎮静」「健歯護持」「歯止祈願」のご利益の他に、
「歯業成就」ということで、
歯科医や歯科技工士などの歯の医療に関わる方々、
歯科医師を目指す学生さん、
歯ブラシ・歯磨き粉・歯に関するガム・入れ歯などの関係者
もお参りに来ているそうです。
私が歯神社を訪れた際の話なのですが、
神社の前に若い女の子4人組とおばちゃん3人組の2グループが、それぞれ参拝と記念撮影をしていました。
参拝と撮影が終わるのを待っている間、おばちゃんグループから話かけられたのですが
管理人はおばちゃんからよく声をかけられる
話を聞くと茨城県から大阪まで観光に来ていたらしく、
ご主人が歯医者さんをされているので歯神社を訪れたと言っていました。
もっとも、本当に困っていたのは「せっかく作った病院のホームページに人が来ないこと」だったようですが・・・
歯神大神さまはウカノミタマノカミ様のことらしいので、「商売繁盛」の御利益もいただけると思います。
それから歯神社では年に一度、6月4日に「歯神社例祭」が執り行われています。
参拝者や氏子の1年間の歯の健康が祈念されるお祭りで、神事の後には先着順ですが、お祓い済みの歯ブラシをいただけるそうです。
6月4日・・・「虫歯の日」だね!
1度その日に足を運んでみたいです。
お守り・御朱印は綱敷天神社御旅社へ!
綱敷天神社御旅社への行き方
歯神社は小さなお社ですので、御札やお守り、御朱印の授与は「綱敷天神社御旅社」で行われています。「綱敷天神社御旅社」は歯神社から少し離れていますが、徒歩でいける場所にあります。
それでは綱敷天神社御旅社までの行き方も紹介しましょう。
歯神社までの行き方で登場した、JR高架下の「EST」の所まで戻ってください。
そして「EST」に向かい合って左、「茶屋町」の方向に進みます。

そのまましばらく歩き「NU茶屋町」を通り過ぎたところに、

大きな石鳥居が見えてきます。
そこが「綱敷天神社御旅社」です。

歯神社のお守りと御朱印
綱敷天神社御旅社の画像です。「天神社」という名前の通り、菅原道真公が祀られていますね。

それから玉姫稲荷大神のお社もありますので、
綱敷天神社御旅社は学問や縁結びに御利益がある神社になります。
そして社務所にて歯神社のお守りや御朱印をいただけるのですが・・・
この日(平日の11時30分頃)はいらっしゃらないようでした。
どうやら神職の方が一人しかおらず、しかも複数の神社を管轄しておられるようなので、とても忙しいみたいです。
午後2時過ぎに再度訪れましたが、やはり不在のようでした。
呼び出しのために社務所窓口にインターホンと、
そして神職が不在で用事があるなら電話をと、電話番号が貼り出してありましたが・・・


「歯神守」のお守りが欲しかったのです

たった500円の買い物のために忙しいとわかっている人を呼び出すのもどうかと思い、今回は参拝だけしておきました。
他の人の体験談によると、土日の午後なら社務所に人がいらっしゃるとのこと。
お守りや御朱印をお求めの際はご注意ください!
おわりに
大阪の梅田は、もともと「埋田」という名前だったと言われています。そのほか「淀屋橋」や「道頓堀」に見られるように、橋・堀といった川や水辺を連想させる地名が今も残っています。
繁華街の今の姿からは想像できませんが、もしかしたらかつては川の水の氾濫などに頻繁に悩まされていた地域だったのかもしれません。
そんな地域で、川の氾濫の「歯止め」が転じて「歯痛止め」になり、
現在では全国から御利益を求めて人が訪れるようになったという変遷は、長い歴史の一幕を見ているようでとても面白いですね。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。