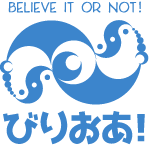この記事の目次
おみくじの起源
おみくじは、もともと神の意志を知るために行われた占いの一つです。古代では神聖で公正な判断として、政治にも利用されてきました。
平安時代、天台宗延暦寺の高僧・良源が延暦12年に始めた「元三大師みくじ」がおみくじの起源とされています。
はじめは漢詩で吉凶を綴っていたものでしたが、江戸時代に入ってから、数あるおみくじの中から一枚を引くという形になり、現在に至ります。
おみくじの順番
おみくじの順番に明確な決まりはなく、神社やお寺によって異なる場合があるようです。7段階のものと12段階のものが有名ですので、この2通りの順番を紹介します。
7段階のもの大吉>中吉>小吉>吉>末吉>凶>大凶
12段階のもの大吉>中吉>小吉>吉>半吉>末吉
>末小吉>凶>小凶>半凶>末凶>大凶
このほか、入れている寺社が少ないために滅多に出ない運勢ですが、「平」が入るものもあります。
この場合だと
「平」が入るもの大吉>吉>中吉>小吉>半吉>末吉
>末小吉>平>凶>小凶>半凶>末凶>大凶
おみくじの「大」と「小」って?
おみくじで「大」と「小」がありますが、大きさの大小ではなく、陰陽五行説の陰と陽を表しています。「大」が「陽」を「小」が「陰」を表しています。
陽 … プラス・能動的・前進・積極的・広がる・発展・造化
陰 … マイナス・受動的・後退・消極的・結ぶ・収縮・融合
幻の運勢!大大吉

日本に数えるほどしか扱っていない幻の運勢「大大吉」。
扱っている寺社は以下の通り。
参拝に訪れた際は是非お試しください!
幻の運勢 大大吉が入っている神社
・岩手県下閉伊郡普代村「鵜鳥神社」・東京都千代田区「靖國神社」
・愛知県蒲郡市「竹島八百富神社」
・岐阜県高山市「飛騨一宮水無神社」
・京都市上京区「護王神社」
・京都市中京区「御金神社」
・京都市伏見区「伏見稲荷大社」「城南宮」
・大阪府吹田市「泉殿宮」
・神戸市兵庫区「松尾稲荷神社」
・広島県福山市「草戸稲荷神社」
おみくじの確率
実は、おみくじには大凶をいれていないところが意外に多いそうです。東京都内で大凶がある神社・仏閣は、776ヶ所中、たった31ヶ所なのだとか。
おおよそですが、大吉を引く確率は20%前後、吉は25~35%くらいとされています。
凶は10%前後の設定が多いようです。
ですが、浅草寺だけ凶の出る確率は30%もあるそうです。
おみくじは持ち帰るべき?結ぶべき?

起源でお話ししたように、おみくじとはもともと神様の意思を聞くためのもの。
ですから本来おみくじは吉凶に関わらず持ち帰るものとされています。
ですが、実際には寺社によっても見解が異なっています。
自分にとって都合の悪いおみくじはその場で結びつけ、さらなる御加護を願うものとする考えもあります。
どうしても吉凶の結果ばかりを気にしてしまいがちですが、大事なことは細かい部分に書いてあります。
細部に書かれた内容から対処法を知り、自分を戒めるきっかけとしましょう。
そして、おみくじはむやみに捨ててはいけません。
神様や仏様と「縁を結ぶ」ため、境内に結ぶのが基本です。
おみくじを結ぶなら、しっかりした目的を意識して結ぶようにしましょう。
おみくじを結ぶ時の注意点
おみくじを木の枝に結ぶのは、「木の生命力にあやかり、願い事がしっかり結ばれますように」
という祈りが込められています。
ただし、むやみに境内の木に結びつけると、木を傷めてしまいます。
「おみくじ結び所」が指定されている場合には、必ず指定場所で結んでください。
木に結ぶ場合、良い結果のおみくじは「松」の木に結びつけると、良い知らせを「待つ」という意味に
逆に、悪い結果のおみくじは「杉」の木に結ぶことで、悪い知らせは「過ぎ去る」という意味になります。
おみくじが示す運勢に応じて結ぶ木を変えるといいでしょう。
おみくじを結ぶ時は利き手と反対の手で結びましょう。
凶の運勢が出てしまっても、利き腕と反対の手でおみくじを結べば、困難な行いを達成するということで凶が吉に転じるとされています。
初詣のおみくじは一回だけ?
初詣のおみくじは何回ひいても問題ないとされています。結果が気に入らなければ、良い結果が出るまで何回もおみくじを引きなおしてもよいのです。
また、占いたいことが幾つもあるのなら、占いたいことを心に思い浮かべて、その都度おみくじを引いてください。
おみくじの有効期限
年始の初詣で引くものだから1年のような印象を受けますが、実はおみくじの有効期限は、願掛けをした日から願い事が成就するまでの期間といわれています。その人自身の解釈でかまわないのです。
持ち帰ったおみくじの処分法
年末年始に神社へ行くと、古いお守りや破魔矢などをお焚き上げするため、それらを納める場所がおおむね臨時で用意されています。テントが設置されていたり、段ボールを置いてあったりと、神社の規模で違いはありますが、その場所の前には賽銭箱が置いてあります。
年に1回まとめて、古いお守りと一緒に、おみくじも納めましょう。
その他、年末年始でなくても神社に行き、「お焚き上げをお願いします」と伝えれば処分してもらえます。