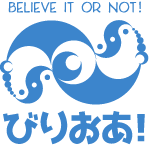今まで開運やパワースポットに関する記事を書いていて、ふとこんなことを思いついたんです。
自宅に神社があれば運気が上昇するのでは……?
神社やパワースポットが近くにあるどころか、パワースポットの中で生活をするわけです。
さらに賽銭箱を置き、お守りやおみくじなどのグッズ販売まで手掛ければ、副収入になるかも。
関連記事 → おみくじの雑学・豆知識まとめ

そんなことを考え、自宅に神社を作ることはできるのか。
できるならどういう手続きが必要で、どれくらい費用がかかるのかについて調べました!
自分の敷地内に神社を作ることは可能!

結論から言いましょう。
敷地内に神社を建てることは可能です。
日本国憲法の条文の中に「信仰の自由を認めること」が明記されています。
個人には神社やお寺を開設する自由が憲法によって保障されているのです。
デパートや会社などのビルの屋上、商店街に神社があるのを見たことはないでしょうか。
お菓子神社や球団神社などの神社が、個人が神社を作った例ですね。
もちろん他人の土地に神社を無断で建ててはいけませんし、
建築基準法に則った建設許可は必要になります。
神社を建立するのは個人の自由な宗教行為なので、包括される宗教団体の規則に基づいて行えば役所などへの届け出は必要ありません。
もっとも、あなたの作った神社が地域住民から支持されるかどうかは別の問題です。
しかし単に神社を名乗るだけなら一向に差し支えないのです。
ただし、宗教法人にする場合には「宗教法人法」に基づく手続きが必要となります。
宗教法人にしようとすると、途端に話が難しくなるのですが……
宗教法人については後ほど説明しますね。
分霊・勧請について

神社を建てるにあたって、通常は神社から分霊していただいてから鳥居などを建てるとことになります。
分霊とは神道の用語で、本社の祭神を他の場所で祀る時に、その神様の神霊を分けたものを指します。
神仏をお迎えすることを勧請といいます。
勧請はもともと仏教の言葉だったのですが、本地垂迹やら神仏習合やらを繰り返した日本の宗教史を経て、神道でも用いられるようになりました。
文法上は「○○の分霊を勧請していただく」という形になります。
それから、“神霊を分けたもの”と表記しましたが、神様が細胞分裂のように複数に分かれるのではないようです。
例えとしてよく用いられるのが“どこでもドア”。
分社には神様が降り立つための“依り代”、つまり御神体が置かれています。
御神体は岩や鏡、刀、隕石だったりする場合があります。
神様はその依り代を“どこでもドア”のように使い、分社に降り立っているのです。
祀る神様を決めるにあたり、御利益から考えるとしましょう。
例えば学業にご利益ある神社にするのであれば祭神様を菅原道真として、既存の天満宮などからご神体の分霊を勧請させてもらうのがよいかと思います。
商売繁盛ならお稲荷様ですね。
関連記事 → 神社の種類とご利益まとめ

分霊について、費用がどれくらいかかるものかはわかりませんでした。
それから神社を作るからといって、神主の資格などを取得する必要は必ずしもありません。
鳥居はどこで買えるの? いくらかかるの?
単に自分の敷地内に神社の建物だけ建て、神様を祀るだけというのであれば、建設費と維持費だけで済みます。それでは鳥居など、神社の建設に必要なものはどこで買えばよいのでしょうか。
神社の建設に必要なものは神具店で取り扱いがあります。
ですが、自宅に鳥居を建てたい人はそんなにいないようで、鳥居などの神社建設に必要なものを販売しているという神具店は、全国を探してもそれほど数はありません。
鳥居専門の業者というのはいくつかあるようです。
神具店や石屋、石材店などが請け負ってくれるようですね。
「京都神具製作所」というお店のHPを見ると、大きさや型式によって値段は異なりますが、一番小さな鳥居で30万円となっています。
これに運搬費用と工事費・設置費が加算される形になります。
参考までにこちらのお店のHPだと、
祠宮 稲荷セット(屋外用)
稲荷用の御神殿、神鏡、稲荷金紋陶器1式、ローソク立て1対
¥198000
賽銭箱(小型) ¥28000~
春日灯篭 ¥400000~
台座 ¥300000~
地蔵堂 ¥500000~
となっています。参考までに。
HPを眺めていると、いくらくらい費用がかかるのかぼんやりわかってきます。
ちなみに、一般住宅の前に賽銭箱を置いて副収入にしても全く問題はありません。
ですが20万円を超えると雑収入として納税の義務が生じますので、その際は所得税を納めることを忘れないでくださいね。
宗教法人を有する神社について

今までは宗教法人を有しない神社の建築について書いてきました。
宗教法人にする場合には「宗教法人法」に基づく手続きが必要となります。
宗教法人にしようとすると、宗教活動の実績や手続き、そして億単位の費用が必要になります。
宗教法人とは
人が集まって集団を作り、一定の活動目的を掲げて行動するためには、団体を組織して活動していかなければなりません。そのために事務所を設け、活動のための財産を所持し、維持・運用していくことが不可欠になります。
公法人や社団法人のように、宗教団体も宗教法人という法人格を取得できます。
神社だと、御祭神を篤く崇敬し祭祀を厳修する宗教的な役割と、神社を維持運営し、神社の財産を維持管理するという機能があります。
そして神社本庁に加盟するためには宗教法人であることが前提条件となっています。
宗教団体が宗教法人になるためには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。
①宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主な目的とし、礼拝施設を整えていること
②現に宗教団体としての実体を有し、他の個人または団体と区別された独自の活動を行っていること
③宗教法人の存立を左右する礼拝施設が負担付きまたは借用のものではなく、長期に亘り安定的、継続的に使用できる状態になっていること
これらの要件を満たした上で、宗教法人となる手続きがなされます。
詳細は割愛しますが、
宗教内部での設立の会議を行い、代表者・代表役員・責任役員を選出
信者および利害関係人に設立の公告を行う
所轄庁(都道府県知事)に規則の認証を申請する
設立の登記
これらの手続きを経て宗教法人格を取得します。
さらに神社を設立する場合だと、神社本庁統理の承認も得なければならず、さらに複雑な手続きが必要になります。
費用はどれくらいかかるの?
宗教法人格の取得は、登記に関わる作業ですので行政書士に依頼できます。ざっと価格を調べると、その場所の物価やサービス内容によって変わると思いますが、
50万円~100万円で宗教法人格の登録を請け負ってもらえます。
神社としての建物、施設、土地について、神社本庁は加盟するにあたって以下の要件を満たすこととしています。
原則として境内地の面積が100坪以上あること
本殿・拝殿・手水舎・鳥居を備えており、神社として相応しい雰囲気を有していること。
本殿等の建物や工作物が神社らしい様式であること
社殿と社務所の各建物も独立していること、祭祀の場と俗務を行う場所が分かれていることが望ましい
神社でお祀りするに相応しい御祭神をお祀りしていること
神社の予算規模が一法人運営に適当な額であること
土地や建物にかなりの費用がかかることがお分かりでしょう。
さらに神社の規模が大きくなってくると、
幣殿、舞殿、祈祷殿、神楽殿、神饌殿、参集殿、絵馬殿、神庫、神輿殿、祭器具庫など
が必要になってくることもあります。
鎮守の杜として、地域の人々の憩いの場となるためには境内林も必要になってきます。
これら一連の施設や環境を造り整備することで、神社は神社として機能するのです。
そして忘れてはならないのは維持費。
建物や所有している彫刻や美術品が文化財に指定されていた場合は、数千万から数億の補修費がかかる可能性があります。
宗教活動の実績を積んでから認可までの間は宗教法人とは認められていませんから、この期間の税制上の優遇は受けられません。
宗教法人格を有する神社を買う・譲り受ける
これまで神社を法人化して宗教法人になる手順と費用について大まかに説明してきましたが、現在では宗教法人格を取得するのは非常に困難になっています。おそらく、オウム事件の影響でしょう。
宗教法人を新たに設立することが難しいなら……
宗教法人となっている神社を買う、または譲り受けるということはできないのでしょうか?
宗教法人も法人であるため、株式会社のように法人の売買・譲渡をすることが可能です。
土地とその上の建築物の取引になりますので、管轄としては神社の売買も不動産屋が取り扱うことになります。
とはいったものの、中古物件やマンションの売買ならともかく、神社を売りたいという人も買いたいという人も、市場にはあまりいません。
最寄りの不動産屋に問い合せても、まず取り扱っていないでしょう。
インターネットを見ていると、公益法人の売買・譲渡を仲介するサイトが幾つか見受けられます。
本気で探すなら、そういったサイトに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
ちなみに神社を購入するとしても法人格の売買は価格が高く、億単位のお金を用意しておく必要があります。
まとめ
日本国憲法で信仰の自由を認めるため、敷地内に神社を建てることは可能神社を建てるにあたって公的機関への許可・届け出は必要ない
分霊の勧請をお願いしよう
自宅に神社を建てるだけなら建設費と維持費だけで済む
宗教法人として神社を所有するなら億単位の費用がかかる
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。