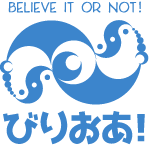初詣やパワースポット巡りで、神社に参拝することがあるでしょう。
でも、一般的には神社にお参りなんて、しょっちゅう行くものでもありませんよね。
私も友人と初詣に行くと、
「鈴を鳴らすのと、礼をするのと、お賽銭投げるの、どの順番だったっけ??」
と毎回聞かれます。
「前の人のマネをしてるよ」なんて人もいらっしゃるのではないでしょうか?
というわけで今回は、神社参拝の順序を、注意点を交えながらまとめてみました!
お寺の参拝について知りたい方はこちら!
鳥居をくぐるときは一礼をしてから

鳥居から先は神様がいらっしゃる神聖な場所です。
鳥居やしめ柱の前で一度立ち止まり、軽く一礼(小揖)をしてから入場しましょう。
左側を通行する時は左足から、
右側通行で歩く時は右足から入ります。
参道は真ん中を歩かないように
参道の真ん中は「正中」と呼ばれ、神様の通り道とされていいます。なるべく正中を避けて歩きましょう。
また、家族や友達、恋人と訪れるからといって大きな声での会話は慎んでください。
参道を歩く時は静かに、内観しながら進みましょう。
手水舎で手と口を清める

必ず、手と口を清めてから参拝しましょう。
水は古くから穢れを洗い流すものと考えられ、参拝の際は、最初に日常でついた穢れを手水舎で落とします。
以下の順番で清めていきます。
手水の順序
①右手で柄杓を持って水をすくい、左手を洗う②左手に柄杓を持ち替えて右手を洗う
③もう一度柄杓を右手に持ち左手に水をため、その水で口をすすぐ
口をすすいだら、使った左手ももう一度水で洗う
④最後に残った水で、柄杓を縦にして水が柄杓の柄を伝うように洗う
古来より日本では左の方が右より格が上と考えられていました。
例えば、左大臣の方が右大臣より位が高く、古い雛人形はお内裏様が左側に座っています。
そのため、神社参拝においても左側を格上とし、優先することが多く見受けられます。
拝礼の際の服装
拝礼の前に服装を整えます。冬であれば、コートやマフラーをつけたまま拝礼するのは神様に対して失礼にあたりますので、脱いでから拝礼します。
神前の立ち方
手を合わせる時も、真ん中の参拝は避けるようにしましょう。なるべく神前の中央には立たないようにし、小さく一礼します。
お賽銭を納める

最近の風潮で、お賽銭は静かに賽銭箱に落とすものと考える方もいらっしゃいますが、基本的な決まりはないようです。
小銭の鳴る音が縁起につながる、という考えもあります。
もっとも神社によっては、お金を投げることで社殿をいためる、人に当たる危険がある場合など、投げてはいけないと定めてある場合もあります。
くれぐれも、お賽銭を力いっぱい投げつける、なんてことは避けましょう。
お賽銭の額は気持ちの問題で、自分の払える範囲でよいとされています。
お賽銭とは神様への捧げものあって、ご利益を買うというものではないからです。
縁起が良いといわれているお賽銭の金額として次のようなものがあります。
お賽銭の金額
5円 「御縁がありますように」
5円2枚 「重ね重ね御縁がありますように」
29円 「 福がきますように」
5円10枚 「 五重の御縁がありますように」
日本らしい言葉遊びですね。
ですから無理にこの金額をおさめる必要はありません。
10円玉は「とおえん(遠縁)」の語感につながり縁が遠ざかると言われているので避けた方がよいでしょう。
「ご縁があるように」と5円、「充分なご縁があるように」と15円。
その他、願いが通るようにと穴の空いた5円玉・50円玉をお供えする方が多いようです。
鈴を鳴らして、二礼二拍手一礼
鈴があれば力強く鳴らしましょう。鈴には魔除けや清めの意味があり、これを鳴らすことにより穢れを祓います。神様の声が鈴の音に似ているという話もあります。
そして二礼二拍手一礼を行います。
二礼二拍手一礼の作法
①「二礼」神前に向かって2回深くおじぎをします。
②「二拍手」
両手を伸ばして掌を合わせてから、右手を指の関節一つ分程度、後ろに下げます。
肩幅ほどに両手を開き、高く音がするように柏手を2回打ちます。
再び両手を合わせてお祈りをします。
③「一礼」
最後にもう1回深く礼をします。
お願い事のかけ方
願い事がある場合は柏手の後に手を合わせた時、心の中で念じますが、手短にしましょう。長い時間、拝殿の前を占有するのは迷惑になります。
実利的な願かけはしてはならないと言われますが、特に願い事が制限されることはありません。
特にお願い事がないようでしたら、神様への感謝の気持ちを心の中で伝えましょう。
丁寧に参拝したい方に、天津祝詞を唱える参拝方法を紹介します。
二礼二拍手一礼の後に、以下の祝詞を唱えます。
高天原に神留まります 神漏岐 神漏美之命以ちて
皇御祖神伊邪那岐之大神 筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原に
身禊祓い給ひし時に生坐る祓戸の大神等 諸々の禍事罪穢を祓へ給へ
清め給へと申す事の由を 天津神 国津神 八百万の神等共に聞食せと恐み恐み申す
<読み>
たかあまはらにかむずまります かむろぎ かむろみのみこともちて
すめみおやかむいざなぎのおおかみ つくしのひむかのたちばなのおどのあわぎはらに
みそぎはらいたまひしときにあれませるはらいどのおおかみたち もろもろのまがことつみけがれをはらへたまへ
きよめたまへともうすことのよしを あまつかみ くにつかみ やおよろずのかみたちともにきこしめせとかしこみかしこみもうす
参拝が終わったら
鳥居をくぐった後、鳥居に向かい直し、再度一礼することが作法となっています。初詣の帰り道は寄り道をしないでまっすぐ帰ったほうがいいそうです。
途中で寄り道などをしてしまうと、せっかく参拝でいただいた福を落としてしまうからです。
お参りする神社の御利益について知りたい方はこちらの記事もどうぞ!